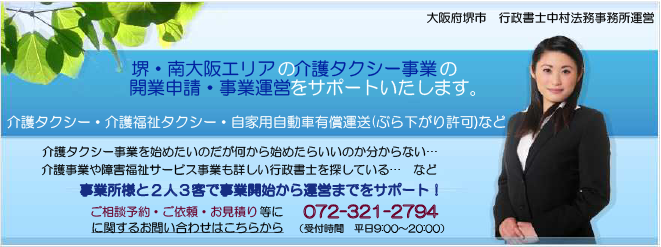身体障害者や要介護者など、一人では公共交通機関を利用することが困難な移動制約者に対して、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを提供する福祉輸送については、基本的には、タクシーなどの公共交通機関がその担い手となっています。
しかし、タクシー等によっては十分な輸送サービスが提供されない場合もあり、公共の福祉を確保する観点から、一定の要件を満たした場合には、NPO等に対し自家用自動車による有償運送することが認められています。
これが、「NPO法人等による福祉有償運送」の制度です。
この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等が行う登録を受ける必要があります。
目次
福祉有償運送の要件について
福祉有償運送の登録を受けるためには、道路運送法における以下の要件を満たしている必要があります。運送の実施主体について
福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人のほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。福祉有償運送は、採算性などの面からバス、タクシー事業者が算入しないような場合に行われるものであり、また、輸送の安全や旅客を確保するためには、運行管理の体制や事故後の処理体制の整備などある程度組織的な基盤が必要と考えられるため、運送主体は、NPO法人等に限られています。
運送の区域
運送の区域は、運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要です。使用できる自動車の種類
福祉有償運送で使用できる自動車の種類は乗車定員11人未満のもので次のとおりです。| 種 類 | 形 状 等 | |
| 福 祉 自 動 車 | 寝 台 車 | 車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車 |
| 車いす | 車いす利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車 | |
| 兼用者 | ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車 | |
| 回転シート車 | 回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車 | |
| セ ダ ン 等 | 自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車 | |
旅客の範囲
運送しようとする旅客の範囲は、次の者のうち、他人の介助によらずに移送することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であって、運送しようとする旅客に記載されている者及びその付添人となります。① 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 ② 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方 ③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方 ④ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害 学習障害を含む)を有する方 |
○ 旅客の名簿に記載されている方については、申請時に会員である必要はありませんが、運送する際には会員になっている必要があります。
○ ③、④の方を運送の対象とする場合には、運営協議会において運送の対象とすることが適当であることについて確認されることが必要です。
○ 透析患者のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎など、運送の態様に基づいて運営協議会で必要性が認められた場合には、1回の運行で複数の旅客を運送(複数乗車)することができます。
運転者の要件
運転者は、自動車の種類に応じて、次の要件のいずれかを備える方でなければ、運転させてはなりません。| 自動車 の種類 | 運転者の要件 |
| 1福 祉 自 動 車 | (1) 第二種運転免許を受けており、その効力が停止されていない者 |
(2) 第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない方であって、次の要件のいずれかを備えている方 ① 国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了していること ② (社)全国乗用車連合会、(財)全国福祉輸送サービス協会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を修了していること | |
| 2セ ダ ン 型 | 福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、次の要件のいずれかを備える方(又はいずれかの要件を備える方の乗務) ① 介護福祉士 ② 国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること ③ 上記(1)②の研修を修了していること ④ 訪問介護員など |
運行管理者の選任
運行者は、運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければなりません。また、5両以上の自動車を運行管理する事務所にあっては、事務所毎に、次の要件を備える運行管理の責任者を、自動車の数に応じて選任する必要があります。
| 運行管理の責任者の要件 | 選任する人数 |
国家資格たる運行管理者 | 39両まで1人、以降40両毎に1人 |
運行管理者試験の受験資格を有している方 | 19両まで1人、以降20両毎に1人 |
| 安全運転管理者の要件を備えている方 |
整備管理者の選任
運送者は、自動車の点検及び整備を適切に実施するため、整備管理の責任者の選任、その他整備管理の体制の整備を行わなければなりません。整備管理の責任者については、特段の資格要件は求められていませんが、整備管理に関する知識を有していることが望まれます。
損害賠償措置
運送者は、自動車の運行により生じた旅客その他の方の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、次の基準に適合する任意保険(共済を含む)の契約を締結していることが必要です。| ① 対人賠償の限度額が1人につき、8,000万円以上のもの |
② 対物賠償の限度額が1事故につき、2,000万円以上のもの |
③ 運送者の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないこと |
④ 保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと |
⑤ すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること |
対価の設定の考え方
対価の基準としては、①旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること
②合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること
③当該地域におけるタクシーの運賃及び料金を勘案して、営利を目的としない妥当な範囲内であり、かつ。運営協議会において協議が調っていること
が必要とされています。
登録の期間
登録の有効期間は、登録の日から2年間となります。運営協議会について
運営協議会は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。また、運営協議会は、移動制約者に必要な輸送を確保し、地域福祉の向上に寄与するよう運送者に必要な指導・助言に勤めるものとされています。
この運営協議会で「福祉有償運送が必要であること」の協議が調った場合、運営協議会の合意があったものとみなされ、「運営協議会において協議が調ったことを証する書類」が申請者に交付されます。
福祉有償運送の必要性が認められる場合としては、次のものが考えられています。
① タクシー事業者等による福祉輸送サービスが提供されていないか、直ちに提供される可能性が低い場合
② タクシー事業者等は存在するものの移動制約者の需要量に対して供給量が不足していると認められる場合
この運営協議会の合意があって、はじめて運輸支局に福祉有償運送の登録を行うことになります。
NPO法人等による福祉有償運送の登録については、こちらの資料も参考にしてください。
>> 福祉有償運送ガイドブック(平成20年3月 国土交通省)
大阪市・堺市・南大阪で介護タクシーを開業したい方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、介護タクシー許可申請、介護タクシー運賃認可申請、運輸開始届出の提出、ぶら下がり許可など、介護タクシー事業の開業・運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
出張対応でお客様のご希望の場所へお伺いしてお話をお聞きしますので、介護タクシー事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
介護タクシーの基礎知識 関連ページ
- 介護タクシー事業の営業・集客の方法 - November 21st, 2024
- 介護タクシー事業許可に必要な書類一覧 - February 8th, 2014
- 介護(福祉)タクシー開業までの流れ - June 12th, 2013
- 訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)について - June 9th, 2013
- 特定旅客自動車運送事業(介護事業)について - June 7th, 2013
- 介護タクシーの必要性 - June 7th, 2013
- 介護タクシーの種類 - June 7th, 2013
- 介護(福祉)タクシーとは? - June 6th, 2013